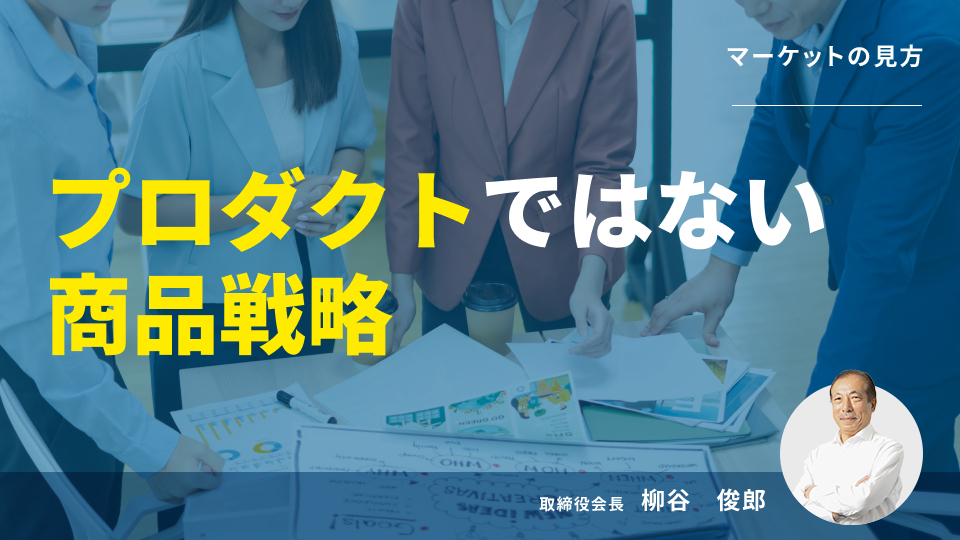
No.574 プロダクトではない商品戦略 ― マーケティングの道 ②―
今週の一句
"人はなぜ 琴線に触れる 時がある なぜかわからぬ なぜを思うか"
新たなプロダクト(商品)企画に日々悩んでいる担当者にとってはびっくりする言葉かもしれませんが『企業が売れると思うものを顧客が購入することはめったにない』という警告を、経営学者ピーター・ドラッカー氏は発しています。この言葉の意味はどういうことなのでしょうか。
まず『企業が売れると思うもの』とはどういうものなのでしょうか。とてつもなく大量の情報が流れる現代では、何が売れているのかというニュースは検索すればすぐにわかります。隠れているように思える情報も、ほとんどの人にとってアクセスすることは難しいことではありません。そうなると、新たなプロダクトを考える人にとっては、その売れている商品よりも、もう少し工夫したものを考えるか、その売れている商品とは異なるテーマで売り出すことを考えるというステップがあります。買い手に“より良いもの”を届けたいという思いは間違いではありません。よくある商品企画会議においては、現在の市場の状況に関しては極めて綿密な分析が示され、他社の商品比較がしっかりと並べられて詳細な説明が行われます。その上で、自分たちが考えた商品の特徴、特に差別化出来ることや競争力などが語られます。この参加者たちは、そこには“より良いもの”があるような気持ちになるのです。会議では新商品が決定されて、様々な準備をして販売が開始されます。そして実際に売り始めると、顧客の反応は悪くないものの、思ったような実績が出ない、といったことが繰り返されます。ここにはどのような問題があるのでしょうか。
他と比較して“より良いもの”というプロダクトを開発すれば、競争に勝って市場を支配出来る力を得られるのではないかという幻想は常に生まれるものですが、ここにはまずもって顧客サイドの視点がありません。『顧客はなぜ購入するのか』というもっとも大切なことを忘れた商品企画のワナがあるのです。すなわち、顧客の立ち位置からスタートすること、そこからのプロセスにこそ競争力のエッセンスがあることを忘れてはいけないのです。真のマーケティングはまだ始まったばかりだと考えるのです。
顧客視点のマーケティング戦略構築に用いられる
「4C分析」のフレームワーク

出所:各種資料を基にあおぞら投信が作成。